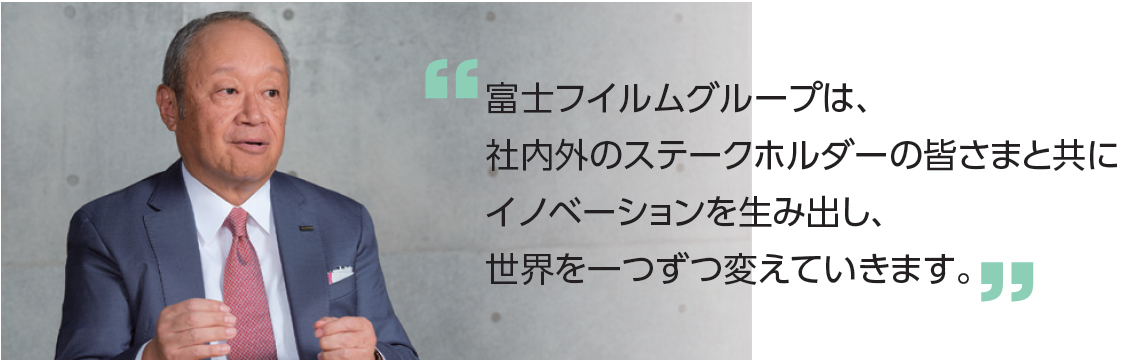3期連続で過去最高業績を更新し、ヘルスケアの売上は1兆円を突破
中期経営計画「VISION2030」の1年目であった2024年度は、昨年1月の創立90周年を機に制定したグループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」の下に全社のベクトルを合わせ、売上高は3期連続、営業利益は4期連続、当社株主帰属当期純利益は5期連続で過去最高を更新しました。全ての事業セグメントが増収を達成した中、ヘルスケアの売上が初めて1兆円を突破し、全社営業利益率が10%を超えたことは中期経営計画の初年度として弾みのつくスタートとなりました。地政学的リスクや自然災害の頻発など不確実性が増大する中でも、当社は社会の変化にアンテナを張り、富士フイルムグループの競争優位性を高めつつ収益性と資本効率を重視した経営を推進しています。これまで強化してきた稼げる力をもって、企業価値向上を確実に実現していきます。
当社グループは1934年の創業以来、社会にイノベーティブな価値を届けるための挑戦と努力を重ねてきました。そして、写真フィルム市場の急速な縮小に伴う本業消失の危機を事業ポートフォリオの再構築によって、新たな成長への最大の好機へと変えてきました。これは、多様な人、知恵、技術を融合・進化させながら粘り強く課題解決に取り組んできた当社ならではのトランスフォーメーション力によって実現できたものと考えています。
以来、事業ポートフォリオを絶えず進化させることで持続的な成長を追求しており、私自身もCEOとしてスピードとダイナミズムを重視した経営判断の実践に努めてきました。2024年度以降も、バイオCDMO(バイオ医薬品開発製造受託)事業では旺盛な需要を捉え、米国ノースカロライナやデンマーク拠点での大型設備への投資を継続したほか、半導体材料事業のさらなる拡大に向けて2024年度から2026年度の3年間で1,700億円以上の研究開発・設備投資を計画するなど、積極的な成長投資を進めています。一方、ヘルスケアのLS(ライフサイエンス)ソリューション事業では、生殖補助医療品事業を売却するなど、より強固な事業ポートフォリオを構築すべく取り組んでいます。
「エコノミック・モート(経済の堀)」を強化し、
勝ちパターンを作る
VISION2030の2年目となる2025年度も、過去最高の売上高、営業利益、当社株主帰属当期純利益の更新を見込んでいます。しかしながら、営業利益計画である3,310億円は、為替影響・米国の関税影響などを勘案すると決してたやすく達成できる目標ではありません。計画達成に向け、現在の不透明な世界経済動向を注視し、長期的な視野を持ちながら、いかなる状況においても変化を捉えて機動的に先手を打っていきます。従業員一人ひとりが鍛えてきたレジリエンスと課題解決力を現場で生かすことで成長戦略を確実に進め、過去最高業績の更新を実現します。
こうした取り組みにおいて私が重点を置いているのが、富士フイルムグループの競争優位性を生かせる成長市場において、市場展開力、開発力、大胆な設備投資を駆使してスピーディーに強い市場ポジションを獲得し、強いブランド・高いシェア・優れた機能性など他社が容易に超えられない「エコノミック・モート(経済の堀)」を築く戦略です。当社グループの独自技術を活用した唯一無二の価値を提供することで、この堀を深く、幅広くし、事業の勝ちパターンを確立していきます。例えば、instax“チェキ”や、 医用画像情報システム(PACS※1)をはじめとするAI技術、イメージセンサー用カラーフィルター材料「WCM(Wave Control Mosaic)」、ネガ型現像液※2など、エコノミック・モートを持つ事業は着実に育っています。これまでに築いた堀を強化するとともに各事業の競争優位性を高め、さらなる投資によって社会への提供価値拡大と企業価値向上につなげる好循環を盤石なものとしていきます。
※1 Picture Archiving and Communication System:X線写真やCTスキャン画像、MRI画像等の医療画像をデジタル化し、ネットワークを通じて管理・配信・運用等を行う仕組み
※2 露光後に感光しなかった部分を現像液で除去して回路を作るネガ型の現像工程で使用される
エコノミック・モートをさらに広く深くし、
事業成長を加速させる
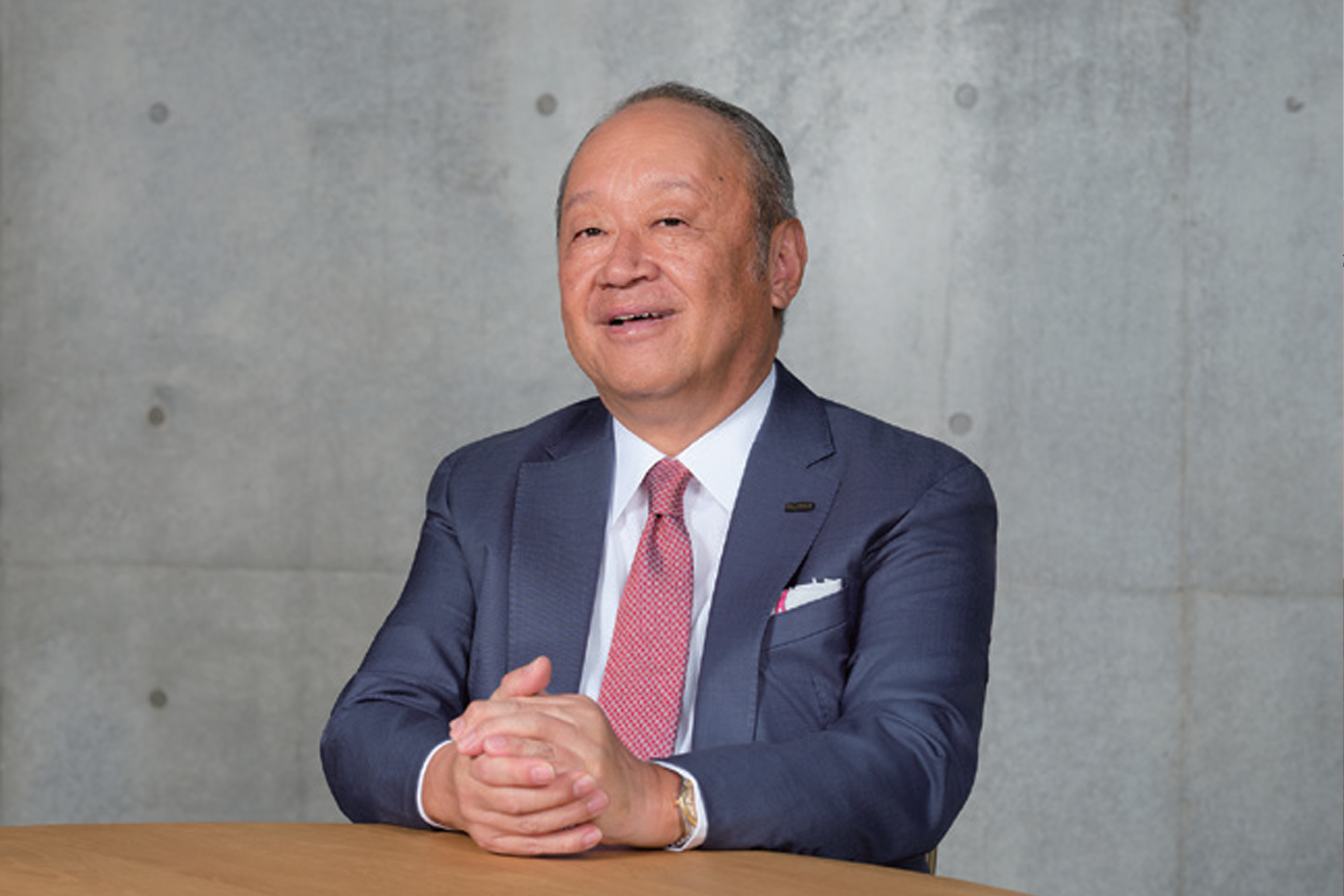
当社が成長領域と位置づけているバイオCDMO事業や半導体材料事業においても、エコノミック・モートを広く深くすることで事業成長を加速していきます。
バイオCDMO事業は、確かな品質の製品を、高い製造能力・顧客の近くに準備してきた最新鋭の製造設備をもって確実に届け続けることでさらなる成長を図っていきます。業界をリードするうえで必要なのは、高度な生産技術と信頼です。当社グループの基幹工場であるデンマーク拠点は、高効率・安定製造を実現しており、これまで積み上げてきた製薬企業からの受託実績がFDA(米国食品医薬品局)やEMA(欧州医薬品庁)などからの各種認証取得実績とともに高く評価されています。そして、ノースカロライナ拠点の新設備も既存のデンマーク拠点と共通の設計・設備・プロセスを展開する「kojoX(コージョーエックス)」アプローチを採用し、安定したサプライチェーンや円滑な技術移管を短期間で可能とする体制を整備しています。このような差別化によって、稼働開始前の設備における新たな案件の受注にもつなげています。本年4月には世界的なバイオ医薬品企業であるRegeneron Pharmaceuticals,Inc.と総額30億ドル超のバイオ医薬品の製造契約を締結したほか、複数の大手製薬会社との長期契約・基本合意を締結するなど、好循環が生まれています。

- 拡大
- 既存のデンマーク拠点と共通の設計・設備・プロセスを
グローバルに展開
また、本年6月には、同事業を展開するFUJIFILM Diosynth BiotechnologiesをFUJIFILM Biotechnologiesに、LSソリューション事業で細胞培養用の培地ビジネスを推進するFUJIFILM Irvine ScientificをFUJIFILM Biosciencesにそれぞれ社名変更しました。これは、グループシナジーをさらに拡大させるとともに、ライフサイエンス市場における富士フイルムブランドのさらなる強化を目的としたものです。タグライン「Partners for Life」のもと、医薬品の研究初期段階から商業生産まで一貫して支援するEnd to Endのソリューションを提供し、世界の製薬企業や薬を待ち望む多くの方々の「信頼される真のパートナー」になることを目指します。
半導体材料事業は、半導体製造におけるさまざまな工程で使用される幅広い製品ラインアップを展開する「ワンストップソリューション」と、世界20カ所の製造拠点・6カ所の研究開発拠点を有することで構築した強じんなサプライチェーンによって顧客への安定供給を行う「地産・地消」、そして迅速なオンサイトサポートを行う「地援」を実現。顧客の多様なニーズや課題の把握、各拠点への技術や情報の共有を通してグローバルな顧客対応や高品質の製品供給にもつなげています。地政学的リスクの高まりによってさらに拡大する、顧客の近隣拠点でサプライチェーン体制を確立する需要にも貢献できており、これまでまき続けてきた成長の種が芽吹いていることを実感しています。また、2030年度に約15兆円規模に拡大することが見込まれるインド半導体市場の成長性を見据え、同国エレクトロニクス製造大手Tata Electronics Private Limitedと、インドでの半導体材料の生産体制とサプライチェーン構築に向けた連携を進めています。今後、半導体産業の集積地を目指す同国・グジャラート州での半導体材料製造拠点の設立も検討し、インド市場への本格参入を目指します。
そして多拠点化が進む大手顧客の厳しい品質要求に対し、本年7月には、グローバルSCM(サプライチェーンマネジメント)・グローバルQA(品質保証)グループを新設。これまで半導体材料の米国拠点を率い、本年6月には富士フイルムの執行役員に就任したFUJIFILM Electronic Materials U.S.A.社長・CEOのBrian O’Donnellyが新設グループを管掌し、供給体制を一層強化していきます。
さらに、当社は写真フィルムや半導体材料の開発を通して培った独自技術を活用し、環境や生態系への影響が懸念される有機フッ素化合物PFAS※3を使用せずに繊細な回路パターンを形成可能なネガ型ArF液浸レジスト※4を開発しました。先端半導体の国際研究機関であるimecと共に、車載や産業用半導体など、幅広く使われる28nm世代※5の微細な金属配線を高い歩留まりで形成できることを実証。半導体デバイスメーカーから高い関心を寄せられており、現在早期の販売を目指して、顧客企業での評価を進めています。今後も顧客との関係性を深めながら共に課題解決に取り組み、半導体産業の発展に尽力していきます。
※3 ペルフルオロアルキル化合物、ポリフルオロアルキル化合物およびこれらの塩類の総称。具体的には、OECDが2021年に公表した"Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance”で示す化合物のこと
※4 ArF(フッ化アルゴン)エキシマレーザー光(波長193nm)を用いる露光手法で、現在最も普及している先端リソグラフィー技術
※5 ArF液浸のシングルパターニングで製造可能な技術の最終世代
AIを富士フイルムグループの
未来を創る原動力に

- 拡大
- 表彰式では、Fujifilm AIChatを用いて「壁打ち」しながら
祝辞を作成したことも披露しました
富士フイルムグループでは、製品・サービスへのAI実装や日常業務におけるAI活用が加速しており、AIは当社グループの成長の原動力となっています。AIを活用したDXを事業競争力の強化やビジネスモデルの変革、社会的価値の提供につなげ、企業価値向上に貢献することを経営戦略の重要なポイントとして、グループ横断で推進。医療分野などの各事業や開発・調達・生産・マーケティングなどの各機能において生成AIを活用した新たな成長・競争力強化につながる価値創出も進んでいます。
また、全ての従業員が生成AIなどの最新のデジタル技術の活用によって生産性を高める取り組みに参画しています。私の発案の下、本年3月に「All-Fujifilm生成AIコンテスト」を開催しました。当社グループのチャット型生成AI利用環境「Fujifilm AIChat」を用いて「笑顔を増やすためのアイデアを創出する」というテーマで募集したところ、国内外から自由な発想に基づいた多数のアイデアの応募があり、それらは社内でも共有されています。従業員の最新技術への積極的な姿勢と熱意に改めて手ごたえを感じています。
当社の経営戦略と連動したDX戦略と一連の取り組みが高く評価され、「DX銘柄2025」に選定されました。
アスピレーション(志)の掛け合わせが
イノベーションを起こす
グループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」の制定から2年目に入り、さまざまなパーパスアクションがグローバルで広がっています。私を含む役員も本年9月までに国内外でのタウンホールミーティングを通して41,900名の従業員とパーパスを起点とした対話を重ねてきた中で、すでに「理解・共感」の段階を超えて、「行動」に結びつき始めていることを実感しています。これから大切になるのはアスピレーションを仲間と共有し、チームで多様なアイデアを掛け合わせながら実行に移していくことです。取り組みを進める中で心に湧き上がる一人ひとりの「成し遂げてみせる」という強い思いがアスピレーションの実現には重要です。その強い思いを抱いた、いわば「スイッチの入った状態」の従業員が目的意識を共有し、アイデアやアクションを掛け合わせてチームで大きな成果につなげていく—これが当社のイノベーションやトランスフォーメーションの源泉です。
例えば、インドをはじめとする新興国で展開している健診センター「NURA」は、ある若手従業員の「新興国における医療格差を是正したい」というアスピレーションを起点にスタートし、成長を続けているビジネスです。NURAでは、当社が持つCT・マンモグラフィなどの医療機器や医師の診断を支援するAI技術を活用して、高い水準の健診と医師による健診結果のフィードバックが約120分で完了するという価値が支持されています。開始から2年でインド、モンゴル、ベトナムと10拠点に広がり、今年度中にはアフリカへの展開も予定しています。健診サービス事業のさらなる拡大に向けた戦略拠点「NURA Global Innovation Center」を2024年12月に開設し、健診サービスのほか、NURAで働く医師、技師、看護師などの専門人材を育成するトレーニングセンターとしての機能や、インド国内のNURAで撮影された医用画像を遠隔で読影する集中読影センターとしての体制も整備しました。世界の医療の発展と人々の健康の維持増進に貢献すると同時に、経済価値の創出に着実につながっています。

健診サービス事業での重要なパートナー企業であるインドの大手ヘルスケア企業「Dr. Kutty’s Healthcare」と共催したNURA Global Innovation Centerのオープニングセレモニーでは、当社の若手従業員とDr. Kuttyの息子さんたちの強いアスピレーションからNURAが始まったことを紹介しました
さらに、私が感動したパーパスアクションとして、インドネシアの孤児院で暮らす子どもたちにinstax“チェキ”で撮影した「初めての家族写真」をプレゼントする取り組みがあります。インドネシアの現地法人の従業員が孤児院を訪れ、instax“チェキ”で撮影した孤児自身の写真を成長の記録として、また、孤児院の仲間たちとの写真を家族写真としてプレゼントする活動を進めてきました。この取り組みが、社内外で多くの共感を呼び、現地のクリエイターや大手出版社の協力によるアートブック『instaxnesia』の出版に発展しました。同国全土での書籍販売による利益は、インドネシアの孤児院7カ所への支援に充てられており、従業員のアスピレーションが社会に笑顔と感動をもたらした実践例だと感じています。
イノベーションは一人で起こすことはできません。アスピレーションを持った多くの人たちが集い、それぞれの思いやアイデアを掛け合わせて、その行動を大きなうねりとしていくことを目指します。社会に貢献する価値を生み出していけるよう、私も現場でのコミュニケーションを大切にしながら富士フイルムグループをリードしていきます。
従業員エンゲージメントサーベイ」の結果から課題
を明確にし、活力のある職場環境をつくっていく
パーパス策定後に実施した2024年度の従業員エンゲージメント調査では、エンゲージメントスコア※6が昨年度の調査に続き高い水準の81%となり、「パーパスへの共感、理解」も高いスコアとなりました。しかし、組織によってばらつきがあるため、サーベイ結果の分析によって課題を明確にしたうえで、各組織で建設的な議論を進め、活力のある職場環境をつくることを重視しています。
そして、世界に在籍する約73,000名の従業員が互いを認め合い、従業員一人ひとりの個の力を発揮できる環境づくりに注力しています。多様な知・経験、そして志を集めてそれらを企業の活力にしていくために、富士フイルムグループでは、「多様なストーリーを認め合う」というビジョンを掲げました。そして具体的なアクションとして2024年10月には性別や国籍、携わる事業の枠組みを超えて、多様性を認め合うフォーラムを開催し、それぞれの従業員の多様なストーリーを認め合う風土の醸成を目指してきました。また、従業員一人ひとりが変化をチャンスと捉えて挑戦を重ねるための「自己成長支援プログラム」をグローバル展開し、従業員の成長を多面的に支援しています。
会社が発展していくためには、従業員が心身ともに健やかであることも重要なテーマです。当社グループでは、2019年に「富士フイルムグループ健康経営宣言」を制定し、CEOを「健康経営最高責任者」、人事部長を「健康経営責任者」とする推進体制を構築して、グローバルで健康経営を推進しています。富士フイルム従業員向け健診施設「富士フイルムグループ健康保険組合 富士フイルムメディテラスよこはま」では、当社のメディカルシステム事業が提供する、最新の医療機器やAI技術を活用した医療ITシステムなどを導入しており、2024年1月からCT検査、2025年5月からMRI検査を開始するなど、従業員に高品質な健康診断や人間ドックを提供しています。これらの健康増進の取り組みが評価され、2020年から5年連続「健康経営銘柄」に選定されています。
※6 各設問の選択肢のうち「肯定的回答(5段階の上位2つ)」を選んだ割合。この数値が高いほど、従業員の主体性や貢献意欲が高いことを示す
資本効率改善への取り組み
当社グループが企業価値最大化を目指すうえで、成長投資に加えて資本効率向上への取り組みも欠かせません。私たちはVISION2030における2030年のあるべき姿として「収益性と資本効率を重視した経営により富士フイルムグループの企業価値を高める」を掲げ、「成長投資と収益性重視」「資本効率の向上」「研究開発マネジメント」「投資リターンの確実な創出」という4つの重点項目に注力しています。
直近の投下資本利益率(ROIC)は、想定WACC(5~6 % 水準)を上回る水準を維持するも、前述のバイオCDMO事業や半導体材料事業への積極投資を背景に投下資本が先行して増加しており、今後さらなる改善の余地があります。これに対して、バイオCDMO事業への設備投資が2024年度にピークを迎えて2025年度から減少に転じるタイミングを捉え、2026年度には全社フリーキャッシュフローをプラス転換させる計画です。引き続き各事業で投資リターンを創出するとともに、収益性を高めていくことで、2030年度目標であるROIC9%以上、ROE10%以上の達成を目指します。
事業ポートフォリオ全体としての力も強化
事業ポートフォリオマネジメントでは、市場の魅力度と自社の収益性の2軸で各事業を「基盤事業」「成長事業」「新規/次世代事業」「価値再構築事業」に分類。当社が高い競争力を持つ「基盤事業」からキャッシュを生み出し、同事業で創出した資金を、中期的に当社の成長を牽引する「成長事業」の強化や、成長を期待できる「新規/次世代事業」に投入していきます。また、成長性・収益性の観点で「価値再構築事業」と位置づけた事業については、収益性の改善や事業価値を高める戦略を策定・実行することで、「基盤事業」へのシフトを図っていきます。このサイクルを中長期視点で回し続け、持続的なキャッシュ創出と企業価値拡大を図ります。
祖業から継続する
サステナビリティへのコミットメント
祖業の写真フィルムは、製造時に清浄な水や空気が不可欠であることに加え、撮影前に品質の良し悪しが確認できない特性上、お客さまに信頼を買っていただく製品です。そのため、富士フイルムグループは事業活動において自然環境から恩恵を受けると同時に、自社の事業活動が自然環境に影響を与えていることを真摯に捉えてきました。これが、環境保全やステークホルダーからの信頼といったサステナビリティの考え方が創業当時から深く根づいている理由です。
そして、富士フイルムグループでは脱炭素社会の実現に向け、原材料調達から製造、輸送、使用、廃棄に至るまでの製品ライフサイクル全体において、2030年度までに2019年度比でGHG排出量を50%削減することを掲げています。また、エネルギー利用効率の最大化と再生可能エネルギーの導入をさらに進め、2040年度までに自社が使用するエネルギー起因※7のGHG排出量実質ゼロを目指しています。そのための施策の1つとして、本年5月に、オランダで写真用カラーペーパーや培地の生産などを行うFUJIFILMManufacturing Europe B.V.の拠点内に、再生可能エネルギー電力を最大限活用する電気ボイラー設備をグループとして初めて導入しました。2025年度には、拠点内で使用するエネルギー起因のGHG排出量を2024年度比で約26%削減する見込みで、当社グループが目指す脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩となります。
※7 製品の製造段階における自社からの直接排出(Scope 1)と他社から供給された電気・蒸気の使用に伴う間接排出(Scope 2)
未来を創造する価値を提供し、
世界中の笑顔の回数を増やしていく
富士フイルムグループがいつの時代においても必要とされる企業であり続けるためには、持続可能な社会の実現に向けて、未来を創造する価値を提供することが何よりも重要だと考えています。企業経営は、必ずしも実力だけでうまくいくものではなく、その時々の社会や事業環境の変化に強く影響されることがあります。当社のこの20年ほどの歴史を振り返っても、私たちはそれを強く意識せざるを得ません。しかしながら、どのような変化の渦中にあっても、私を含め従業員一人ひとりがアスピレーションとそれを「成し遂げてみせる」という強い思いを持って、一歩でも半歩でも前に進む努力が必要です。変化を成長のチャンスと捉えて挑戦する。日々直面する課題に怯まず、考え抜いてベストな決断を導き出す。そしてその決断に基づいて迅速なアクションを起こしていく。この積み重ねによって、世の中の流れやチャンス・運気のようなものを私たちのもとに引き寄せることが可能になるのだと感じています。富士フイルムグループは、社内外のステークホルダーの皆さまと共にイノベーションを生み出し、世界を一つずつ変えていきます。私はCEOとして、これからも攻めの経営を行い、その責任を果たしていく所存です。そして、価値ある製品・サービスを社会に提供して獲得した利益を原資に、「事業への再投資」「人材育成・労働環境整備」「ESG課題への取り組み」「株主還元」を進め、企業価値の向上に確実につなげていきます。
私のアスピレーションは「100年先の未来に有益なものを残す」こと。富士フイルムグループ約73,000名の従業員のアスピレーションが重なり合い、化学反応を起こした先に新たなイノベーションを生み出します。社会的価値と経済的価値の両面から地球上の笑顔の回数を増やしていくべく、まい進してまいります。