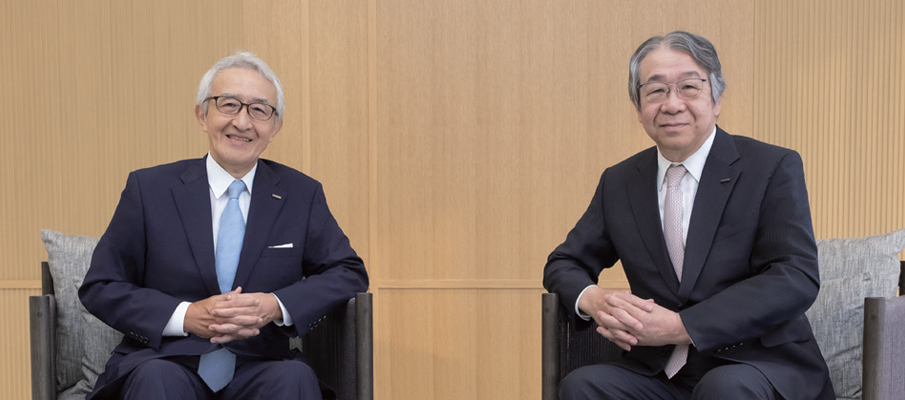助野︰私は、2023年から執行を離れ取締役会議長としての役割に専念していますが、取締役会の実効性を高めるにはどのような議論の在り方が望ましいのか、常に自問自答してきました。近年の日本企業を取り巻くガバナンスに関する議論は、かくあるべしといった形式論に偏りがちですが、私が最も大事だと考えるのは、適切なアジェンダの設定と、自由に意見を交わせる雰囲気の醸成です。これこそが、議長の最も重要な役割です。そのうえで社外取締役の皆さんに求めたいのは、各々の専門性に基づいた多様な視点、すなわち幅です。一方で、社内の取締役に求めたいのは、現場に根差した専門的知見、つまり深さです。この幅と深さを調和させ、掛け合わせることで議論の質の向上へとつなげていくことが、私の最大の責務であると考えています。
また、執行側が議案を説明する際に、往々にして社内の作法や視座、共通認識に基づいた話に偏って、社外取締役に十分に意図が伝わらない場合もあります。そうしたときは執行側に背景説明を促し、必要に応じ私自身がフォローするほか、取締役会に上程されるまでの議論プロセス等も補足することで、社外取締役としっかりと情報を共有しています。加えて、新たに当社グループに加わった海外子会社のトップに自身の事業への考えや展望を語ってもらう場を設けたほか、今後は証券アナリストの方を招いて意見をうかがうなど、社外有識者の方々と双方向の対話を行う場を設ける等の工夫もしていきたいと思います。これにより、取締役会の実効性がさらに高まっていくことを期待しています。
永野︰ガバナンスの目的はただ一つ、企業価値の持続的な向上、すなわち会社を良くすることに尽きます。機関設計の在り方や取締役会の構成員に関する定量基準等は手段の一つにすぎません。その会社が籍を置く国の歴史・風土や企業文化、人材の特性等を総合的に勘案したうえで、どの手段の組み合わせが最も企業価値向上に資するかを、それぞれの会社自らが考え抜き、主体的に選択していくべきです。また、執行側と取締役会の信頼関係も重要です。お互いに自由に発言でき、あらゆる情報を共有できる透明性があってこそ、課題やリスクを率直に議論できるはずです。
加えて、会社を強くするには執行メンバー自身が自律性を持ち、強くならなければなりません。こうした点でも、やはり形式ではなく中身が重要です。社外取締役が取締役会の過半か否かに関わらず、正しい結論に至るまで議論を尽くすことが肝要であり、そのためにも、正しいアジェンダの設定が必要です。そして、長期視点から本質的なテーマを扱い、執行が抱える課題やリスクを包み隠さず取締役会の場で共有することが大事です。その積み重ねによって、執行側と取締役会の間に信頼関係が築かれ、取締役会が本質的な役割を果たすことができると考えます。

助野︰加えて、私が社外取締役の方々に常にお願いしているのは、当社が創立以来90年超にわたり受け継いできた企業文化や技術、マーケティングなどに根差した事業活動が、世の中の価値観から見て乖離していないかをチェックしていただくことです。社外取締役の専門性や幅広い視点からのモニタリングは極めて重要であり、大きな役割を果たしていただいています。
永野︰私自身の経験からも、社内の常識が世間の非常識であることはよくあります。だからこそ、私たち社外取締役が「それはおかしいのではないか」と問題提起し、世間の常識の観点を喚起していくことが欠かせません。その意味でも、証券アナリストや事業の専門家に取締役会へ来てもらい意見を交わすことは非常に有意義です。私たちが感じる違和感や疑問を共有し、アナリストが日頃どう見ているかを知ることで相互理解が深まるほか、取締役会が普段から率直に議論していることを認識いただくことで、株式市場との信頼関係や透明性を高めることにつながります。これはアナリストに限らず、顧客を含む幅広いステークホルダーとのエンゲージメントにも当てはまることです。

助野︰形式を整えても実効性が損なわれては意味がありません。取締役会でどのような議論をしているかをアナリストに直に見ていただくことは、永野さんがおっしゃった通り非常に有益です。私たちは「オープン、フェア、クリア」という企業風土のもと、健全な経営を続けてきました。今後もこの企業風土を大切にし、事業活動全般において透明性や客観性を担保していくことで、それが当社の業績にも結実するものと考えています。こうした考え方も含め、当社にとって何が真に取締役会の実効性向上に寄与するのか、今後も対話を通して説明責任を果たしていきます。
永野︰例えば、機関設計について日本企業全体で見れば依然として約6割を監査役会設置会社が占め、残りの多くが監査等委員会設置会社。指名委員会設置会社はごくわずかです。機関設計を変更したら企業価値が向上するかというと、そんな単純な話ではありません。真に必要なのは、いかにフランクに議論し、本質に迫れるかです。本来、機関移行の議論は期待される効果と併せてなされるべきで、安易に形式を変えるのではなく、取締役会においてもきちんと議論し、説明する努力を続けることが重要です。

永野︰私はこの会社の強みは人材にあると実感しています。人を育てるというよりも、勝手に育つための自助の力を高める環境や気づきの場を整えることが非常に上手いことが当社の強みです。その具体例が、STPDと+STORYに象徴される学びやジョブローテーションによる多様な経験です。そうした学びと実践の行き来を通じてゼロから一を生む力を育み、自助の力を最大限に生かして個人の成長と会社の成長を結びつけているのです。
現在の役員や執行の中核メンバーもこうした環境で育ち、2000年代以降の事業構造の急速かつ大幅な転換期においてもさまざまな挑戦をしながら、自身の成長と会社の成長のスパイラルアップを経験してきました。一方で、現在の若い世代は社会的な貢献を重んじる傾向が強く、会社の成長や業績向上のみを目指してひたむきに働くということだけではついてこないところがあると思います。そこで、昨年制定したグループパーパスを生かして、自律性や主体性をさらに引き出すことによって、個人の成長と会社の成長のベクトルを合わせながら持続的な社会貢献を実現していくということが大事になります。当社には多くの社会課題への取り組みがあり、社会的価値を経済的価値につなげる機会が豊富に存在します。これらは二項対立ではなく相互に動態的に結びつくものであり、この二項動態経営こそがこれからの時代に求められるのではないでしょうか。
助野︰人材戦略においては、健康経営からウェルビーイング経営へと世の中の関心が広がっています。私自身がこだわり続けているのは、月に一度は製造や研究の現場に出向き、従業員たちと直接対話することです。そこで必ず伝えていることが二つあります。一つは、私たちは先輩から文化や技術を受け継ぎ、それをさらに高めてきたが、今度は私たちが次の世代に引き継いでいくということです。そのためには優秀な人材を惹きつけ続ける必要があり、従業員に対して「自分の職場で働くことを自分の子どもに勧められるか」、という視点で自職場を見直してほしい、それを自分事にしてほしいと伝えています。もう一つは、現在の仕事を将来後任に引き継ぐ際、前任者から受け継いだものに、必ず自らのプラスアルファを加えて渡してほしいということです。この二つの話は、現場の従業員たちにとても響きます。
永野︰まさにその通りだと思います。自分の仕事や職場を家族に誇れることは非常に大切で、私も海外で話をするときにそのことを伝えると、相手の目が輝きます。それはたとえ国の歴史・風土や企業文化が違っても、普遍的に言えることだと思います。
一方で、潜在的な課題もあります。今後、新規領域や成長領域の事業が順調に発展し、軌道に乗った際に驕りが生じる可能性、世代交代やM&Aによる人材の流動で当社の企業文化が薄れてしまう懸念です。世の中で、仮に従業員が1つの会社で40年勤めるとすれば、10年経つと会社の4分の1のメンバーは入れ替わることになります。その会社が培ってきた企業文化は意識しなければ次第に変質し、失われかねません。当社もこれを強く意識して、当社の企業文化を継承する必要があります。加えて、グローバル人材の育成において最も大事なのはアイデンティティです。日本人であれば日本人としての自然観や歴史観、文化観を持つこと、さらには富士フイルムグループとしてのアイデンティティを備えることが欠かせません。
助野︰もう一つ、新任役職者研修で私が必ず伝えているのは、相手へのリスペクトを忘れないということです。新しく当社グループに加わった会社の人たちに対し、自分たちの考え方を一方的に説くのではなく、相手がどこまで理解しているかを見極め、相手の立場に立って理解を得る努力が必要です。そうでなければコミュニケーションは空疎となり、本当に伝えたいことが伝わりません。海外の現場でも、ローカル人材と良い仕事をするには、相互リスペクトと相手の立場を踏まえた対応が不可欠だと考えています。
永野︰とても大切なご指摘だと思います。また、相手を一方的に自社のやり方に合わせさせる同化戦略ではなく、包摂戦略を取ることが基本だと思います。ただ、当社グループが大切にしていることやグループで働く意義、強みといった、基盤となる部分はしっかりと理解してもらう必要があると思います。

助野︰私は社長在任中に当社の事業ポートフォリオを整理し、横軸の収益性と縦軸の市場成長性の4象限で、各事業を分類しました。投資のための原資であるキャッシュを生み出す基盤事業、収益性が高く将来の成長が見込める投資対象としての成長事業や新規/次世代事業の両方を持ち合わせている当社ポートフォリオの強みを踏まえたうえで、価値再構築事業については調整が必要だと言えます。当社はこれまでも最適なポートフォリオを目指して、常に適切なチューニングを行ってきました。今後もためらうことなく見直し、取締役会で議論を重ねながら、やめるべきものはやめる。投資すべきものにはしっかりと投資を続けていく。こうしたメリハリある資源配分は、将来にわたる当社の持続的な成長を考えたとき、避けて通れません。
永野︰重要なのは、4つの事業セグメント全体で当社のポートフォリオをどう安定させるかです。金融の視点から見ると、適切なポートフォリオを組むことで、ある事業が不調でも別の事業が支えることで、全体を安定させることが可能です。それは短期的な効率を優先して事業の入れ替えを求めていくこととは相容れません。それぞれの事業を保有する意味をいかに株式市場にお伝えし、理解を得られるよう努めるか。当社の事業ポートフォリオが、セグメント間でどのように支え合い、補完し合うことができているのか、技術や人材等のシナジー効果がいかに発現しているかも含め、その構造を取締役会で継続してモニタリングしています。
そのうえで、あらためて当社は、中長期的に目指すポートフォリオの姿を示し、収益構造の再構築や撤退を含む方向性を明確にしながら、株式市場との対話を続けていかなければなりません。例えばビジネスイノベーションセグメントは現在営業利益700億円台半ば、利益率6%程度ですが、VISION2030では2030年度に10%以上を目指す方針です。これが実現すれば、グループ全体の収益変動幅を縮小し、安定性を高める効果があります。異なる成長ステージや市況サイクルにあるさまざまな事業を抱える中、そのように安定的に利益を生み出す事業を持つ意義は、相応に高いと考えます。こうした当社の事業ポートフォリオの強みをより明確に示し、保有する意味を説明し続けることが大事です。
助野︰ROEを上げていくことは当然のこととして、重要なのはその方法です。私はいたずらに分母を減らすことにのみ注力するのではなく、分子を上げていくことが本質だと考えています。資本効率の観点から、私が社長時代から重視してきたのがROICとCCCです。いずれも役員報酬の評価軸に組み込み、併せてESGの観点からはカーボンニュートラルへの貢献度やエンゲージメントサーベイ結果も評価指標とすることで、資本効率の向上や持続的な成長に対する執行の貢献期待を明確にしています。事業部は利益を稼ぐだけではなく、効率性や持続的な成長性にどれだけ寄与できているかということも重要です。私はこうしたメッセージをこれまで発信し続けてきました。今ではこの考え方は全社に浸透しており、各事業での取り組みを継続することで健全な形でROEを改善できると考えています。
永野︰今後は、ROEを将来的にどの水準まで高めるのか、資本をどう使うのか、基本的なプリンシプルを株式市場と共有していくことが大切です。例えば、助野さんがおっしゃったようにROE向上は利益の持続的な成長によって実現させる、あるいは余分な資本は持たないといった原則。そのプリンシプルに従って将来的なROEの目標水準や株主還元政策についての当社の考え方を明確に示し、投資家の理解を求めることが重要です。
助野︰ありがとうございます。最後に、当社が株主・投資家の皆さまに将来にわたって報いていくためには、やはり多様なステークホルダーに価値を提供していくことが欠かせません。従業員が誇りや働きがいを持てる職場環境の実現や人材育成への継続的な投資、お客さまに新たな価値や感動を届けるための新製品開発や設備投資、そして株主の皆さまへの還元という持続的なサイクルを回し続けていくために、今後も取締役会での本質的な議論をさらに追求していきます。